コミュニケーション能力が高い人は、「聴く力」が高いと言われます。
質問して回答を得る力のことではなくて、耳を傾けて聴く力のことです。
つまり、相手から発せられた情報を聞いて理解することを「聴く力」と表現されているのです。
ここで私が気になっているのは、情報を理解するという部分についてです。
理解の深さは、人によって違います。同じ文章、同じ情報からであっても、人によって理解の深さが異なってくることは、わかったつもり~読解力がつかない本当の原因~(著者:西林 克彦、出版:光文社)を読むと、わかりやすいと思います。
自分のコミュニケーション能力を向上させようと思ったら、読解力の向上は必要なのではないでしょうか。
この記事では、読解力の向上の必要性について述べてみたいと思います。
コミュニケーションに限らず、自己成長にも必要な力なので、ぜひ、あなたも一緒に考えてみてください。
理解の深さは受け取る側で異なる
同じ情報に接しても、受け取る人によって理解の深さは異なります。なぜなら、情報は誰かの脳というフィルターを通ることで、元の情報とは変化するからです。
例えば、会社の朝礼で、朝の報道番組から得た経済情報を紹介しようとするときのことを想像してみてください。
朝の報道番組のキャスターが話した言葉や内容を、そのまま紹介するのではなく、その経済情報から、あなたが周囲に伝えたいメッセージを含んで要約し、紹介するはずです。
そして、あなたの伝えたいメッセージを含んだ情報は、周囲の社員の脳内でさらに変換されることになります。
情報を受け取った周囲の社員は、全員が同じ行動をとるでしょうか。10人いれば、10人とも違った行動をとるはずです。
伝えたいメッセージは、受け取る側によって異なるものになるのです。そこには理解力や価値観など、様々な要因が考えられますが、伝えたいメッセージや情報が等しく伝わるということはあり得ません。
自分が受け取る側の時、理解できているか
情報を自分が受け取るときはどうでしょうか。
相手が発信している情報を理解できているでしょうか。
まぁ、理解できていない人はいないと思います。
問題は、その理解の深さです。
得た情報を他の誰かに説明できる程度に理解できているか。その情報について更に説明を求められたとき、答えることができる程度に周辺情報を集めているか。
冒頭にも書きましたが、わかったつもり~読解力がつかない本当の原因~(著者:西林 克彦、出版:光文社)を読むと、私たちは、「わかった」を「よりわかった」という状態にすることは、かなり困難な作業であると言えます。
つまり、誰かの情報を聞いて、その場で理解したつもりであっても、もしかしたら「わかったつもり」の状態で、浅い理解でしかない可能性があるということなのです。
理解力は頭の良さではない
人と人とのコミュニケーションにおいて、理解力が発揮されるのは、頭の良さではありません。
交わされる情報に対する知識レベルや価値観などによって、その理解度は大きく左右されます。
例えば、オートバイに乗ったことがない人にツーリングの楽しさを伝えたいと思って、言葉を駆使して伝えたとします。
風を切る感覚や、走行速度で体にかかる風圧の感触の違い。カーブを曲がるために遠心力に逆らって車体を傾けていく感覚。車体を操っていると感じる操作感。長時間姿勢を変えられないことで感じる疲労感と目的地に着いた時の達成感など。
しかし、オートバイに興味がない人は深く理解しようとはしないでしょう。内容がわからないということはないし、会話は成立しますが、興味も関心もない情報に対しては、それ以上わかりたいと思わないのです。
つまり、より深く理解するかどうかは、頭の良し悪しではなく、その情報に興味や関心があるか、価値を感じるかということによるのです。
読解力を高めるおすすめの方法
自分が情報を受け取る側であるとき、自分にとって興味や関心がある情報、価値がある情報であれば、より深く理解したいと思うはずです。
そこで重要になるのが「読解力」です。
読解力とは、単に文章を「読む」だけではなく、書かれている内容を正確に理解し、文脈や筆者の意図、登場人物の感情、さらには背景情報までも読み取る複合的な能力のことをいいます。
それでは、読解力を向上させるには何をすればいいのか?それには読書がおすすめです。
ただし、文字を追うだけの読書ではありません。本を読み始める前にこう思ってから読んでください。
- 読み終わったら、本に書かれていた内容を家族に教えてあげよう。
- 読み終わったら、読んで良かったと思ったところを3つ、その理由と合わせて投稿してみよう。
- 本の著者が、本に込めたメッセージが何なのか、その目的は何かを考えながら読んでみよう。
本を読み始める前に、本を読み終わった後のアウトプットを予定しておきましょう。
そうするだけで、理解度はぐっと深まります。本当にアウトプットするかどうかはお任せしますが、できれば実際にアウトプットしてみてください。
読み終えたばかりなのに、思い出すのに苦労する経験ができます。
まとめ:まずは本を読もう
周囲の人との会話の中で、『あれ?この人わかってなさそうだな』と感じた経験がある人もいるでしょう。
理解の深さは、確実に個人差があります。
自分の理解が浅いと、深めるための時間を必要とします。
同じ情報から得られる理解を深くすることは、時間を短縮することにもつながります。
理解力、読解力は高い方がいいですよね。
文化庁が行っている「国語に関する世論調査」によると、1か月に1〜2冊以上の本を読む人は、4割未満。6割以上の人は1冊も読まないと回答しています。
(※令和6年1~3月実施 16歳以上の個人6,000人を対象に行い、有効回答3,559人)
得られる情報量の多さから、Googleなどの検索結果に動画があれば、文章で読むよりも映像で見るという人も多いからでしょう。
しかし、あえて読書をすることをお勧めします。
文章から得られる情報は、自分の頭の中で想像力を掻き立て、思考を活性化させるからです。
紙の本、電子書籍、いずれの方法でも、文章から想像力を使って理解していくことで、より多くの知識を深く得ることができるはずです。
本を持ち歩くのはちょっと。という人でもスマホは持ち歩いているでしょう。
スマホにKindleアプリを入れておけば、ちょっとの隙間時間を使って本を読むことが手軽にできます。
どんな形でもいいんです。本を読んで、想像力を働かせ、『なぜ?』と思う読解力を養いましょう。
それでは、また。
※Kindleアプリは無料でインストールできます。電子書籍は有料ですが、Kindle Unlimitedという定額料金で対象書籍が読み放題になるサービスもあります。初回30日無料体験実施中。詳しくはこちら。
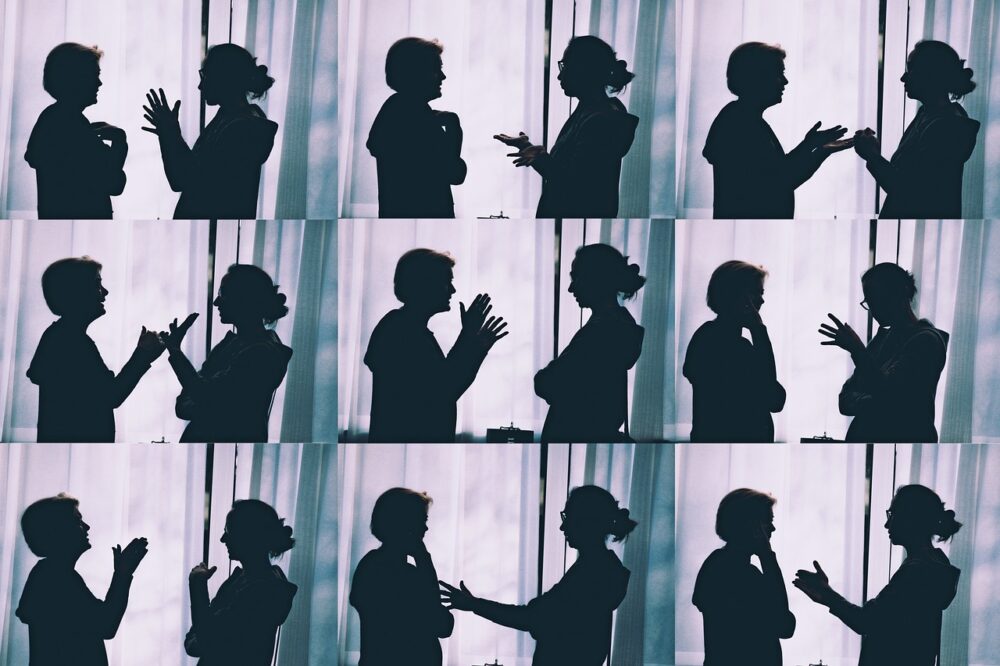


コメント